
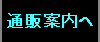
 懐かしいの坂下.探索.8.
懐かしいの坂下.探索.8.
坂下伝統の花馬ですが・・
坂下は大昔から坂下三郷といわれています・郷とは
集落ですが.下組.合郷.町組の三郷です・・下組は今の握.西方寺.高部.外.
合郷は大門.時鐘.矢渕.赤田.町組は .本町.新町.新田
大きく分けたものですが・・それぞれの組の庄屋から
出発することに決まっていました.下組は西方寺訂正.外.井織屋.(今は丸太屋酒造)
合郷は矢渕の吉村酒屋.(今は中学校裏の若宮神社).町組は松井酒屋・・
おそらく新田の松井歯医者ではないかな・・・歯医者の前は酒屋を
営んでいたらしいです..ただ組の倉庫は本町の中部電力の出張所跡
にあったらしいです.(今は順番ですかね)
馬の背に麦.栗.大根.南瓜などの初物を載せて神社にお供えするもので
これらが今の色紙に代えて365本(1年の日数)の花串をさして真ん中の紙の榊は
12段(1年の月数)に折っているもので
本来は馬の背に載っている物は神の召し上がり物で
榊は絹の反物でこれが.氏子の奉る神幣帛です
下組.合郷.町組と順に氏子の長老は先導して威儀を正し
若い衆は元気に笛.太鼓.鼓を鳴らし舞踊り絢爛の花馬を
引き立てる
文献資料は西尾一郎さんからの物を参考にしました
西尾さんは.戦前.戦後.長い間.坂下神社の神主さんとしておられました
新町の竹屋呉服店の長女をもらい.格式高い家柄でした
息子さん達も学校の先生をされていました
竹屋呉服店.宗太郎さんは教育委員.町議.商工会長.などを
勤めた偉い人でした.嫁さんは丸太屋酒蔵からもらわれました
お隣どおしで.隅々まで.いろいろ知ってましたよ...ほぼ毎日のように
隣へ遊びに行っておりました・・・店長が.初めてTVを観たのも竹屋でした
 下組の花馬.丸太屋酒造で
下組の花馬.丸太屋酒造で
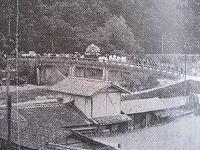 坂下橋を渡る下組の花馬
坂下橋を渡る下組の花馬
 坂下駅に集合した3組の花馬
坂下駅に集合した3組の花馬
正面の二階建ての建物は日通坂下営業所.斜め隣は初音食堂で
すぐ横は中津銀行坂下支店です(訂正.恵那信用金庫坂下支店)..昭和37年当時です
 大正13年時の花馬祭り
大正13年時の花馬祭り
道幅が広いので伝馬町の通りだと思います
左の松月旅館か吉村辺りですかね
坂下には酒造会社が2件あり.山内酒造と丸太屋酒造があります
.丸太屋酒造は創業が明治13年でして祖母の仁応(におう)さんが
九十九歳まで生きられたことから最初の酒銘が長命としました
長命はかなり売れましたが.すでに他に登録されていて
酒銘を変えなくては.なりませんでした.変えた酒銘が仁応で
祖母の名前をつけて売り出した.が.県外持ち出し禁止でしたので
販売路を中津川を中心に広げて行きました・
後に太公望.芭蕉.などもだして序所に販売網を広げていきました
山内酒造>詳しくは当店のHPから
大きなオートバイを乗って集金と御用聞きによく来られました
少し口元の辺がおかしな.かっこう.になっていて..
どうしたんだろうと.小さい時に思っていましたが.
昭和26年9月の記事から宮の洞の友人日下部氏宅で用事を済ませて
山道を帰宅中.子連れの大熊にでくわし.5分間.必死の格闘をしました
手.顔などに一ヶ月の重症をおい.川上診療所に収容されたそうです
ここで調べ物をしている最中に目に止まった記事がありましたので
昭和28年作文コンクールでの物です.全文です
私のお母さん
五ノ三 落合富美恵
私のお母さん今 横浜へ行っていて.食堂屋で働いています
時々手紙もきます.書いてあることは.こんど帰って行きます.
とか病気で行けませんと書いてあります.
また私のやる手紙に書いてやる事は.気をつけて早く丈夫になって
ください.とかいてやります
また.お母さんの方から.お金のつごうが悪いときは.こづつみ.がきます
その中に入って来る物は.さいほう箱.と洋服.とパスイレなど家庭に
やくにたつ.物ばかりです.私はよく歌を歌います.私の歌う歌
はおおかた悲しい歌です.
その歌を歌うとお母さんの事を思いだして.なみだが.ぼろぼろと
でてきます.このあいだ.学校で歌を歌いました.ちょうど家庭の時.お母さんの生活
の勉強をしていました.そしてお母さま.という歌を歌いました
私はその歌を歌ったら.もう なみだがでてきました.私はお母さんのかわりに
台所をします 私達は毎週月.水.金.と朝起会があるけれども
朝早くから台所の仕事をしなければならないので.
いけたくても.いけませんので朝起会には行く事ができません
私には妹も兄もいます.妹の名前は貴美子で兄は和行という名です
兄は私のやる事はあまりてつだって.くれないので.私はたいへん.ざんねんに
思いますが.だれにも まけずに.いっしょうけんめいで働いています
私はこれからもしっかりと勉強をしておてつだいも.がんばってやって
おとなになったら.りっぱな人になろうと思います
以上. 五ノ三 落合富美恵さんの作文全文です
これを見た時.感動して涙がとまりませんでした
ちょうど実家の兄(雅俊)と一緒位の歳でしょうか.
3月に亡くなったのですが
随分苦労していました.父母を守り.店を守りで・・・
今 先進国といわれる国々の中で一番.核家族化がすすんで
います.なにが大事なのか.この事が一番大事ではないでしょうか
話を戻して 坂下探索にいきます
木材工業がさかんになっていました
二つの大きな木工センターがありました.坂下町木材工業共同組合と
東部林産協同組合がありました
昭和22年に帝室林野局坂下出張所(後の坂下営林署)が出来て特売をうけらりる
ようになったのが..大きな発展につながった
 黍生に在った時の東部林産貯木所
黍生に在った時の東部林産貯木所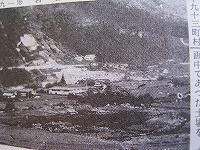 東部林産貯木所移転予定地.昭和37年頃
東部林産貯木所移転予定地.昭和37年頃今の木材市売りです
現在の山口の発電所から川沿いに下り左側一帯が貯木所( 黍生).きびゅうと.
よみます・・昭和17年に木材統制令がだされて同時に日本木材株式会社が
全国に半官半民が誕生した.その下に県本社.地方に地区本社が
できて統制されました.その事務員に丹羽秋夫さん(坂下製材).
藤原信男さん(藤原木工).がいて所長に今井彦太郎(ひらのや)さんがいました
坂下製材は旧弥栄橋の入り口.左側一帯にありました・・
 坂下製材所
坂下製材所今のセレモニーホールの辺りです
川上に向かって奥に長くて大きな製材所でした
藤原木工は今の伊藤歯医者の所にありました・スレート造りで
大きな扉を引くと中に機械がおいてありました・藤原木工の
隣の森治商店との隙間が1m位あり奥に長くて本宅の前に
池がありました...
木工業としては当時木曽の上松の下駄つくりからヒントをえて
三人の人が共同で始めたのが始まりで同時に糸魚川太郎一さんが
東京資本の木工下駄を製造したのが坂下の木工業の元祖だと言えます
共和木工は岐阜の共立木材柿内氏と糸魚川多吉さんが共同で造った
大きな会社です.小県木工は戦時中.金属が不足して.家庭内にあるもの
でも提供していました.そんな時.木製バケツなどを大量に生産して
いました.それが全国に評判が広まり大きくなりました
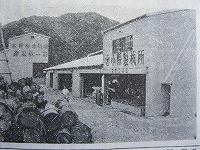 小県製材所
小県製材所糸魚川太郎一さんは昭和25.6年頃には本町で糸魚川酒店として
営業しておられました.もともと中津川銀行坂下支店の
所です.以前は東美銀行としてあった物です.
細い道を奥に入って行くと左側に伊藤歯医者があり.前に
杉山医院の新宅で郵便業務も行っていました
道を挟んで反対側は小県歯医者があり隣が弓矢さん宅で
医院の前に大きな井戸がありました
...徐々に.本町から中心の伝馬町に
移って行きました.今ある郵便局は坂下病院で診療所として行って
おりました.直ぐ道下に園原医院もありました..
坂下病院は国保として昭和15年に創立されて.当時松井忠一.(茶碗屋)
松井恭平(歯医者).松田幸男達がご苦労なされまして
28年に国民健康保険 厚生大臣賞を頂きました.30年に現在の坂下支所
の場所に移りました.
<1に戻る><2に戻る><3に戻る><4に戻る><5に戻る>
<6に戻る><7に戻る><9に続く><10に続く>
<11に続く><12に続く><13に続く>
<14に続く><15に続く><16に続く>
つづきは次回で お楽しみに